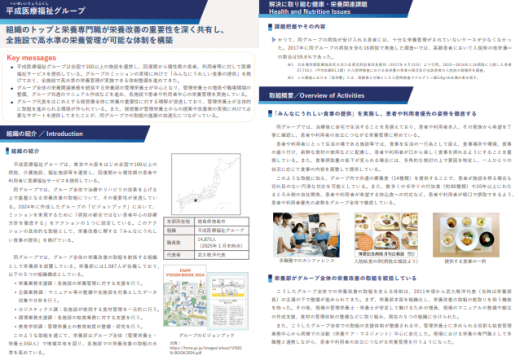当院では、地域の医療機関と互いに理解を深め、より良い連携のために交流の機会を設けています。今回、徳島赤十字病院の職員の方々をお迎えして地域交流会を開催し、当院の概要や「回復期リハビリテーション病棟」における多職種連携の体制などについてご案内しました。この記事では、「食べる力」と「排泄の自立」に焦点を当ててご紹介します。
気管切開からの早期抜去とカニューレ離脱を目指す:多職種チームの挑戦
回復期リハビリテーション病棟では、多職種で連携し、患者さんが在宅復帰に向けて生活に必要な機能を再獲得できるよう支援しています。「口から食べる」支援では、入院時に気管切開や各種チューブを必要としていた患者さんに対して、退院に向けて可能な限り抜去を目指すアプローチを行っています。
国際会議で紹介された取り組み

入院時に経管栄養で栄養管理を余儀なくされていた患者さんに対しても、早期から嚥下内視鏡(VE)や嚥下造影(VF)を用いた評価を行い、段階的に訓練を重ねています。その結果、多くの患者さんが口からの摂取へ移行しています。
これは、早期からの嚥下内視鏡(VE)等による客観的な評価や嚥下リハビリテーション、看護師・特定看護師による医療用チューブ類の管理など、専門性を備えた多職種連携体制に支えられています。さらに、病棟にかかわる管理栄養士が多職種と連携して、個々の患者さんの状態に合わせた「栄養ケア」を実施。管理栄養士による「ミールラウンド」、低栄養状態の改善と経口摂取への移行促進などに加え、365日異なる献立の提供など、「食べる喜び」を支える工夫もしています。
このような取り組みはグループ全体として注目され、国際会議N4Gパリ・サミットにおいて厚生労働省より『誰一人取り残さない日本の栄養政策』の事例として世界に紹介されています。
自立排泄へのアプローチ

「自分の意志でトイレに行き、排泄できる」ことは自立した日常生活に欠かせない要素です。当院では、尿道カテーテル抜去からマイパンツ移行までを段階的にサポートし、チーム医療で排泄自立をめざしています。入院時の評価をカンファレンスで共有し、定時排泄誘導や残尿測定を行いながら経過を観察。膀胱直腸障害のタイプに応じたプログラムを実施しています。その結果、リハビリパンツからマイパンツへ移行できた患者さんは20%※となっています。
ブレイクタイム
当院菓子工房特製のケーキとコーヒーをを囲み、リラックスした雰囲気の中で交流が広がりました。

リハビリ機器の体験
後半は、当院で実際に使用しているリハビリ機器を体験いただき、実際の使用方法や特徴について体験いただきました。
- Phisybo
- OriHime
- IVES Pro
- BMI(Brain Machine Interface)
- 嚥下訓練機器
- 会場の様子
Phisybo:股関節の動きを検知し、モーターで足の「振り出し」「蹴り出し」をサポートする歩行アシスト機器
OriHime eye + Switch:視線を使ってパソコン入力などができる意思伝達装置
BMI(Brain Machine Interface):「動かしたい」という脳の信号を読み取り、手足の動きをサポートする
IVES Pro:脳の信号と実際の動きのずれを補い、麻痺した筋肉の再学習や力加減の練習を助ける
嚥下訓練機器:飲み込みに必要な筋肉や神経を刺激し嚥下機能の回復をサポートする(各種機器あり)
意見交換とこれから
体験後の意見交換では、「紹介後の経過はどうなっているか」「重度から軽度まで幅広く受け入れ可能で信頼感がある」など、率直に語り合い、理解を深める場となりました。ご参加くださいました徳島赤十字病院の職員の皆様、貴重なお時間をありがとうございました。
(※いずれも平成医療福祉グループ内部調査データに基づく)
こちらの関連記事もあわせてご覧ください!
病院へのご質問やご相談は、お電話にてお寄せください。
博愛記念病院 TEL088-669-2166(代表)